こんにちは。
ワタナベミエです。
今回の記事は、融資リスケ時の返済額についてです。
近年、2度目以降のリスケに対して元金返済ゼロを認めない傾向が強まっています。銀行はPL(損益計算書)上の経常利益を返済財源とみなし、その7〜8割を年間返済額に置くのが一般的です。
しかし、それは理論上の返済財源に過ぎません。実務では資金繰りの実態を踏まえないと、現実的な返済は組めません。本記事では、このジレンマを整理し、現場で使える解決策を提示します。
最近のリスケ傾向:元金ゼロは通りにくい
従来は「利息のみ」の据置期間が比較的許容されやすい場面もありましたが、近年は2回目以降のリスケで元金返済ゼロが容認されにくいのが実情です。銀行はPLで経常利益が出ているなら理論上キャッシュが出ているはず、という考えから、経常利益×70〜80%を返済原資として求められるケースが目立ちます。
例えば、経常利益が1,000万円なら、その700万円~800万円を返済財源として要求されるイメージです。
理論と実態のギャップ:利益があってもお金がない
しかしここで問題となるのが、「PL上の利益」と「実際の資金繰り」は一致しないことがあるということです。たとえば、
- 売掛金の回収が遅れるということは:帳簿上は黒字でも入金遅延で現金不足。
- 在庫の増加は:利益は出ていても資金は在庫に固定化されている。
- 成長投資の前倒し:利益計上とキャッシュインのタイミングがずれる。
このため、PLの利益を根拠に返済額を設定しても、実際の資金繰りが回らないケースは少なくありません。
しかもリスケに至る企業ほど、資金繰り管理が弱い傾向があり、日繰り・週繰りの作成ができず、経営者自身が「資金の動きを把握できていない」という実態があります。
銀行側のジレンマ:本部説明と現場実態の板挟み
銀行員の立場から見れば、
- 元金ゼロは「再生の意欲が弱い」と評価されやすく、本部稟議が通りにくい。
- 財務指標上、利益が出ているのに元金返済猶予を続ける合理性を説明しづらい。
といった事情があります。結果として、現場は実態を知りつつも「経常利益の◯割」という理論値を前提に条件設計せざるを得ない場面が生まれます。
しかし現場では、「実際に返済できるかどうか」は資金繰り表を精査しなければ判断できません。
帳簿上の利益≠返済財源ではないことを理解しつつも、形式的に「経常利益の〇割」を返済条件に組み込むジレンマがあります。ここに、企業と銀行の認識ギャップがでてきます。
あなたはこんな悩みありませんか?
チェックリスト
- 2回目以降のリスケで元金返済を要求され、返済負担が重い
- 帳簿は黒字なのに返済資金が不足しがち
- 資金繰り表を作ったことがない/資金繰りを作成してもどう運用していいかわからない
これらは珍しい悩みではありません。次章で今すぐ着手できる解決策を提示します。
解決策:実態ベースで「返済できる条件」に落とす3ステップ
では、どうすればこのギャップを埋められるのでしょうか? ポイントは以下の3点です。
資金繰り表を前提とした交渉
- 入出金のタイミングを可視化と売掛回収の遅延リスクを視覚化する
- 仕入等の支払いの集中月を表面化させる(繁忙期の前倒し仕入 等)
- 一時的支出できれば大型支払い月(賞与、納税、更新設備費、車両入替 等)を織り込んだ月繰り12か月ローリングを用意
これにより「理論上は返済原資があるが、この月は落ち込む」という根拠を示し、資金繰りに合わせた返済額を組むなど現実的な条件に調整できます。
銀行の伴走支援を活用する(作成と運用の定着)
経営者の資金感覚をアップデートする(利益≠キャッシュ)
まとめ:鍵は「見える化」と「共有」
2回目以降のリスケで元金ゼロが通りにくいのは、もはや前提です。だからこそ、PLの理論値だけでなく資金繰りの実態を見える化し、銀行と情報共有することが不可欠。経営者が資金繰りの要点を理解し、銀行がそれらに即した柔軟な対応を取れるかどうか…。
ここに、事業再生の成否がかかっているのです。



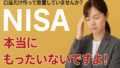
コメント