~本部に物申す、あの頃の支店長たち~
こんにちは。
ワタナベミエです。
銀行員の本音シリーズ、今回は支店長編の第2話をお届けします。
あの頃の支店長は、本部にも遠慮しなかった
私が銀行で働き始めた頃、支店長という存在はまさに「現場の主(ぬし)」でした。
本部からの指示があっても、「この地域ではそんな方針は通用しない」「その案よりこっちの方が効果がある」と、現場の判断でやり方を変える支店長が珍しくなかったのです。
会議でも、上席の意見に「それは現実的ではありません」とズバッと言う。
誰にでもできることではありませんが、それが支店長という役職の“重み”でもありました。
今思えば、よくそんなことができたなと思います。
でも当時は「それが当たり前」で、むしろそうでないと部下からもお客様からも信頼されない時代だったのです。
ポリシーがあったから、部下はついてきた
私がある支店にいた頃の支店長は、とにかく筋の通った人でした。
「お客さまにとっても、うちの銀行にとっても、正しいと思える判断をしろ。どっちにも媚びるな」と、よく言っていました。
あるとき、本部から「ノルマ達成のために、とにかく投信を売れ」とのプレッシャーがかかったときのことです。
その支店長は部下を集めて、こう言いました。
「商品を押し売りして、後で“損した”って言われるようなことは絶対にするな。目先の数字より、お客さまとの関係を優先しろ」
正直、その言葉を本部が聞いたら怒られそうな内容でした。
でも支店内の空気は、明らかに引き締まりました。
私も「この人のもとでなら頑張れる」と、心から思ったのを覚えています。
誰のための仕事か——問い続ける姿勢
今の銀行はマニュアルが整備され、支店長の自由度は少なくなりました。
でも、あの頃の支店長たちは「誰のための仕事か?」という軸を常に持っていたと思います。
それが時にお客様であっても、時に部下であっても本音で向き合う。
それは衝突を恐れない覚悟のある支店長だからこそできたことです。
もちろん、時代が変わり、価値観も変化しています。
昔のやり方がすべて正しいとは言いません。
でも、今でも支店という現場に必要なのは、数字だけを追いかける姿勢ではなく、「自分の信念を持つ」リーダーの背中なのではないでしょうか。
まとめ:支店長は“現場の顔”であってほしい
最近では、支店長が自分の意見を言うことにためらいを感じているように見えることがあります。
それは、本部に遠慮しているのか、お客様に嫌われたくないからか。
でも私は思うのです。
自分の意見を持たないリーダーに、人はついてこない。
昔の支店長には“骨”がありました。
だからこそ信頼され、支店全体を一つにまとめることができたのだと思います。
次回の記事は 『銀行員の本音シリーズ第3話 : お客様と“本音”で向き合った支店長』です。
関連記事はこちら
▶︎【支店長の保身】責任を押し付けられた部下のリアル
【支店長の保身】責任を押し付けられた部下のリアル | ミエ’s ファイナンスノート


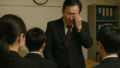

コメント