こんにちは。
ワタナベミエです。
今回の記事は、学歴主義の銀行支店長の実態をお話します。
学歴至上主義の支店長たち
銀行という組織には、「学歴」しか誇るものがない支店長が少なくありません。
「あいつは最終学歴が○○だから出世は無理だ」
「自分は△△大学だから将来有望だ」
そんな言葉を平気で口にし、まるで大学の偏差値が一生の価値を保証するかのように振る舞うのです。
彼らの目には「人間の能力=学歴」という単純な図式しか存在しないように見えます。
数十年もの間、銀行で働いているにも関わらず、まるでついこの間、大学を卒業したかのような言い分や、昔の栄光を追いかける姿は、時がとまっているのかと思ってしまうほど滑稽です。
高学歴のプライドと「実力なき鼻高々」
ただ、その「高学歴」といっても地方銀行の支店長クラスでは、地方国公立大学出身者が多く、全国規模から見れば決して誰もが羨む超名門ではありません。それでも彼らは胸を張り、「自分は優秀だ」と信じて疑わないのです。
しかし現実はどうでしょうか。部下を鼓舞するリーダーシップもなく、顧客から厚い信頼を勝ち取る胆力もない。あるのは「俺は○○大学」という看板だけです。
そしてそういう支店長に限って、他人を見下しながらも「自分は銀行でどんな実績を残したのか」を語ることは一度もありません。学歴を武器にしているつもりが、実際には学歴に寄生しているのです。
高収入なのに貯蓄が少ない支店長たち
銀行員は比較的高収入の部類に入りますが、意外にも貯蓄が少ない支店長は珍しくありません。投資や資産形成を顧客に指導する立場でありながら、自分の財布事情はお寒い限りなのです。
例えば、ある支店長の家庭では「お金を持たせると全部使ってしまう」という理由で、奥さんから自由になるお金をほとんど渡されず、必要なときには家庭内で“お小遣い申請書”を書かされる仕組みになっていました。奥さんの承認印がなければコンビニ弁当すら買えないのです。
また別の支店長は、キャッシュカードを持たせてもらえず、どうしてもお金が必要で奥さんに内緒でカードローン口座を開設しました。借りては返済し、また借りて…を繰り返す姿は、顧客に「計画的にご利用ください」と説く銀行員とは思えないほど滑稽です。
結局のところ、「高収入=金融資産がある」とは限らない。むしろ高収入の割には貯められない、そんな支店長像が銀行には少なくないのです。
ストレスと浪費が生み出す「虚しい自尊心」
銀行の支店長という肩書きは、かつては「地域の顔」でした。しかし今では、上からのノルマに追われるただの「消耗品」です。 数字を管理することは得意でも、人を育てたり企業と深い信頼関係を築いたりする余裕はほとんどありません。
だからこそ、彼らは「学歴」という一枚のカードにすがります。実績や資産を残せない以上、「俺は○○大学」という過去の栄光に縋るしかないのです。 その姿は、タバコとお酒に散財して自尊心を満たすのと同じで、どこか虚しさを漂わせています。
銀行における支店長の役割とは何か
本来、支店長に求められるのは「学歴」ではなく「実績」です。
・どんな困難な融資案件をまとめたのか
・地域企業とどのような信頼関係を築いてきたのか
・どれだけ部下を育て上げたのか
これこそが支店長を評価する基準であるはずです。
しかし現実には、酒席で「俺はどこ大学」と繰り返し、学歴マウントで自尊心を支える支店長が存在します。顧客も部下も、その姿に心底うんざりしているのです。
まとめ:学歴神話の先にあるもの
学歴を鼻にかける支店長の姿は、一種のブラックジョークです。
高収入でありながら貯蓄はなく、健康を害するほど酒とタバコに依存し、家庭ではお小遣い申請書を書かされ、カードローンでしのぐ。そんな支店長が「俺は有望だ」と胸を張る姿は、むしろ滑稽です。
銀行の支店長が「学歴」にすがる姿は、時代錯誤でありながら、この業界の縮図を映しているのかもしれません。
残せるのは「実績」と「信頼」だけです。 学歴を振りかざす支店長の背中を見て、あなたはどんな銀行を信頼できると思うでしょうか。そういう支店長は、銀行でどんな実績を残したのか誰も思い出せない。
結局のところ、銀行員としての「価値」は学歴ではなく「実績」でしか測れないのです。
そして、学歴しか誇れない人は、実は学歴そのものを裏切っているのです。
銀行という組織がそうした人材を支店長に据えている限り、この業界が「時代遅れ」と揶揄されるのも当然ではないのでしょうか。
関連記事はこちら
▶︎銀行員の本音シリーズ 第4話 : 語る支店長より、支える支店長に─銀行員が見た“器”の違い | ミエ’s ファイナンスノート



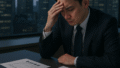
コメント