こんにちは。ワタナベミエです。今回は、ある店舗型サービス業のフランチャイズで起きた融資相談をもとに、
「借りられる」と「返せる」はまったく違うというテーマをお話しします。
表面上は“うまくできた話”に見える
相談に来られたのは、地方都市で新規店舗をオープンしようとするグループ会社。フランチャイズ本部(親会社)―加盟店(子会社)―運営会社(孫会社)の多層構造です。子会社は店舗不動産を保有し、孫会社が実際の運営を行う仕組み。親会社は加盟料、子会社は賃料を得て、孫会社が現場を回す──
書面上はそれぞれ収益源があり、一見すると「うまくできた収益モデル」に見えました。
実際のリスクは“孫会社”に集中していた
実際に運営する孫会社は自己資金ゼロで、改装・備品・人件費などを含む約1,000万円の借入を検討していました。
孫会社の社長は現場経験はあるものの、経営準備は不十分で収支計画もどこか他人事の印象。親会社や子会社は手数料・家賃で安定収入を得ることができて、孫会社が赤字でも痛手は限定的──
最も弱い立場の会社が最大のリスクを背負う構造でした。
要点: お金の流れと責任の所在が複雑で、外部からは健全性を確認しづらい。銀行が融資に慎重になる典型的なパターンです。
銀行が嗅ぎ分ける“危ない匂い”の正体
- お金の流れが複雑で、スキームが見えにくい: 誰が本当の経営者なのか分からず、問題が起きたときの対処も不明確。
- 運営会社の体力が弱い: 自己資金ゼロ。現場経験はあっても、経営に必要な数字感覚や資金繰りの理解が乏しい。
- 「借りること」が目的化: 「融資を通すか」に意識が偏り、返済原資をどう作るかという本質議論が不足。
「借りられる=返せる」ではない
経営者の中には「借りられるならそれでいい」と思う方もいますが、実際は借りられることと返せることは別問題です。
返済は毎月淡々と続く“現実”。融資が実行された瞬間から、事業は資金繰りと返済の両立という新たなステージに入ります。
無理な借入は、売上前提が少し崩れただけで赤字化し、軌道に乗る前に資金が尽きてしまうことも珍しくありません。
銀行が重視するのは、継続して返せる力です。そのためには、経営者がどれだけリスクを自分のこととして引き受けているかが核心になります。
借りる前に“立ち止まる勇気”も経営判断
- 自己資金は総投資額の10〜20%を用意しているか。
- 上位会社(親・子)は保証・出資・手数料減額などでリスク分担するか。
- 保守的シナリオ(売上ダウン・人件費アップ)でも返済可能か。
- 運転資金は3〜6か月分を別枠で確保しているか。
- 「誰が意思決定し、誰が責任を取るか」を契約書で明確にしているか。
経営は勢いだけで走り出してもうまくいきません。いま一度立ち止まる勇気も立派な経営判断です。
借入額を増やすことが目的化していないか、自分のリスクをきちんと理解しているか。確認を怠ると、あとで返済に追われ、事業も人生も苦しくなります。
まとめ
上記の見直しがないままでは、銀行からは融資は難しいと判断されるでしょう。事業融資は「借入できる」ことよりも「続けて返済できる」ことが重要。
返せる確信が持てないなら、設計をやり直しましょう。
経営を安定させるのは資金調達のスピードではなく、リスクを見抜く冷静さです。借りる前に、次の二つを自問してください。
- これは本当に返せる計画か?
- 誰がリスクを負い、誰が利益を得るのか?
借りる前にこの二つを考えてみてください。――それが、無理のない経営と、長く続く事業への第一歩になります。



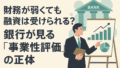
コメント